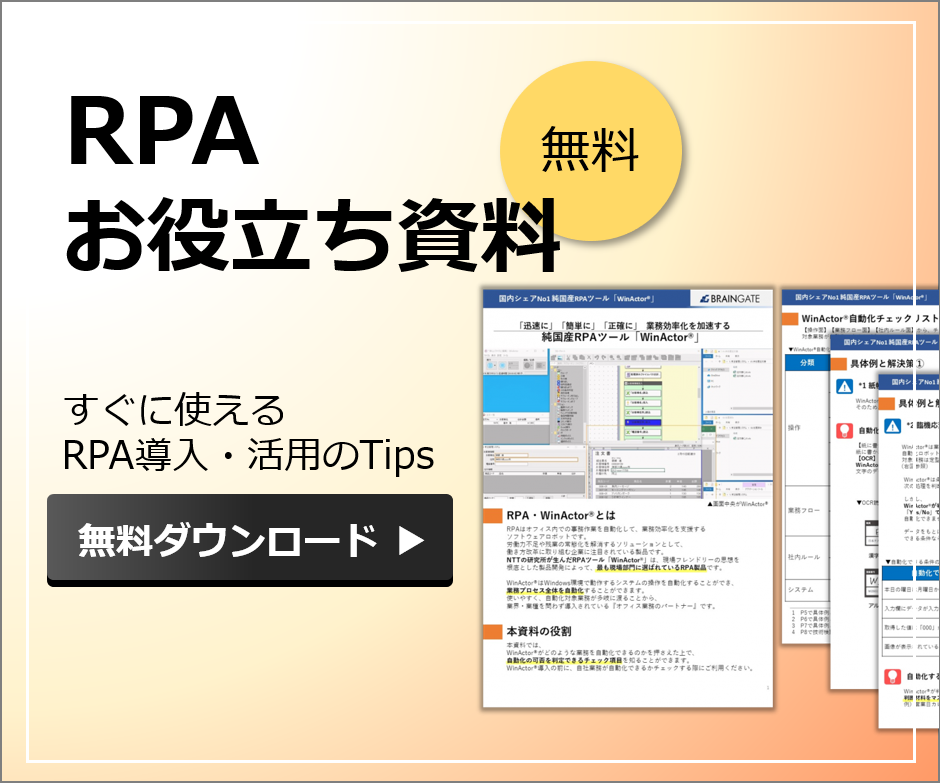【担当者必見】RPA導入がうまくいく会社・失敗する会社の違いとは?
RPA(Robotic Process Automation)は、繰り返しの多い定型業務を自動化することで、業務の効率化と人的ミスの削減を実現する強力なツールです。中でも「WinActor」は日本国内で高いシェアを誇り、多くの企業や自治体で導入が進んでいます。
しかし、現場の声を聞いてみると、「導入したのに使われていない」「最初は盛り上がったが、今は誰も触っていない」といった声が少なくありません。RPAを“導入すること”自体が目的になってしまい、その後の定着や活用がうまくいかない企業が多いのです。
そこで今回は、WinActorなどのRPA導入において「うまくいく会社」と「失敗する会社」の違いを解説し、自社での導入成功に役立つポイントをご紹介します。
RPA導入が「失敗する会社」の特徴
IT部門だけで完結させようとする
RPA導入をIT部門主導で進めた結果、現場の業務実態を正確に反映できないことがよくあります。現場と乖離した自動化は、使いにくくなり、結局使われなくなってしまいます。
現場の声を拾わずにシナリオを作成
RPAのシナリオは、実際にその業務を日々こなしている人の知見が不可欠です。「このタイミングでポップアップが出る」「この例外処理が多い」など、マニュアルにはない現場特有の事情を無視して作成されたシナリオは、途中で動かなくなるリスクが高いのです。
目的が「最新技術の導入」になっている
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」や「業務改善」の旗印のもと、明確な課題解決ではなく“流行に乗るため”に導入するケースも失敗しがちです。RPAは「目的」ではなく、「手段」です。
成果が見えずモチベーションが続かない
導入後、業務時間がどれだけ削減されたか、どんな効果が出たかを可視化できないままでは、現場も管理者も熱が冷めていきます。社内で「RPAって効果あるの?」という声が出ると、次第に使われなくなっていくのです。
RPA導入が「うまくいく会社」の特徴
一方で、RPAをうまく活用して業務改善を加速させている企業には、いくつかの共通点があります。
スモールスタートで始める
最初から大規模な業務すべてを自動化しようとせず、「月5時間削減できる業務から始める」など、小さく始めて成功体験を積み重ねていきます。
現場主導でプロジェクトを進める
実際にその業務を行う担当者を巻き込み、RPAの設計段階から関わってもらうことで、実用性の高いシナリオが作成され、現場でも受け入れられやすくなります。
業務の棚卸しを徹底する
RPA導入の前段階で、業務フローの可視化や「自動化できる業務/できない業務」の分類をしっかりと行います。ここを疎かにすると、非効率なまま自動化してしまうリスクがあります。
成果を社内で共有する
「月間〇時間削減」「ミス削減率〇%」など、数字での成果を定期的に共有し、他部門への導入を促進。モチベーション維持にもつながります。
RPA導入成功のための5つのポイント
- 業務フローの整理・可視化
→ 無駄な業務を洗い出し、どこをRPAに任せるべきか明確にする - 現場担当者の教育
→ 操作方法だけでなく、「RPAとは何か」を理解させることで活用度UP - 導入チームの設置
→ IT部門と現場のハイブリッド型チームがベスト - KPI設定と効果測定
→ 「何をゴールにするか」を明確に。例:月50時間削減、作業ミス0件 - 運用ルールの整備
→ 誰が、いつ、どのように運用・保守するのかを明文化しておく
導入失敗から復活した企業のストーリー
ある中堅製造業では、社長主導でWinActorを導入しましたが、半年後には「現場で使われていない」と問題になりました。原因は、IT部門のみでシナリオを作成し、現場の協力を得ないまま進めてしまったことでした。
そこで方針を転換。現場の担当者を巻き込み、どの業務に負荷がかかっているかをヒアリング。小さな業務からスモールスタートで改善に取り組んだ結果、「週に3時間かかっていた請求書作成が、ボタン1つで完了するようになった」と大きな成果を得られました。
その後は成果を社内共有しながら、別の部署にもRPA導入を展開。今では年間200時間以上の業務削減につながり、「RPA=業務改善の象徴」として、社内の認識も変わりました。
このように、一度失敗してもやり直せるのがRPAの柔軟さであり、WinActorの魅力です。
まとめ
RPA導入の成否は「導入後の定着と活用」にかかっています。
WinActorは、正しく運用すれば確実に業務効率を改善する力を持っていますが、それを活かすには現場を巻き込み、目的を明確にし、小さな成功体験を積み上げることが欠かせません。
RPA導入で迷ったら、「まずは小さく始めて、社内の信頼を勝ち取る」ことを意識してみてください。