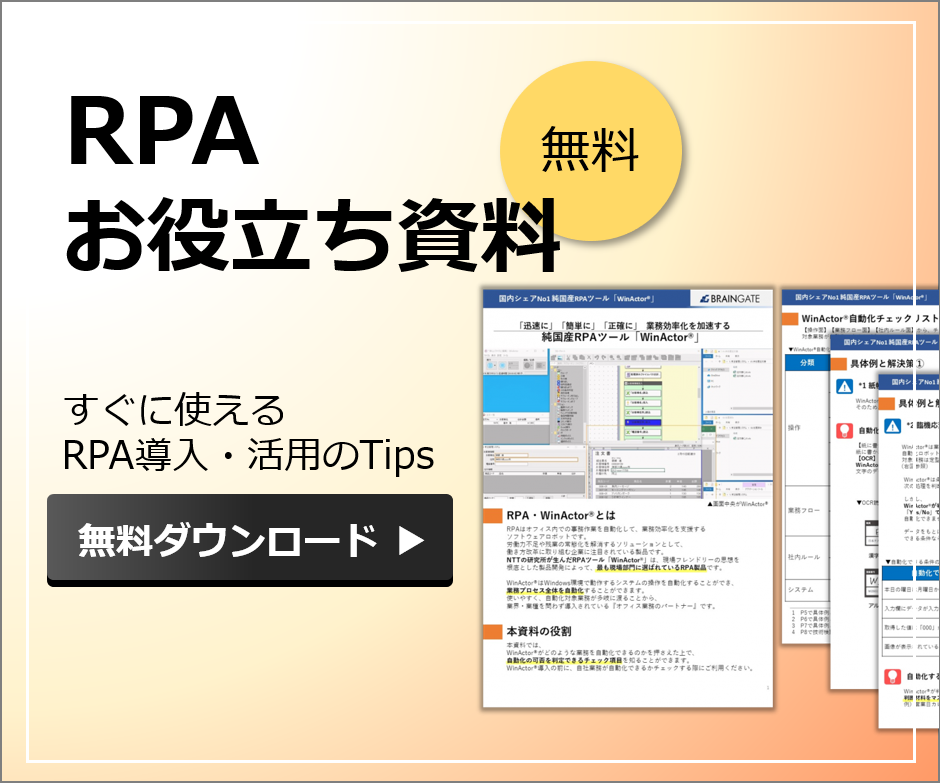WinActorとPower Automateの違いとは?選び方のポイントを徹底解説
1. はじめに:RPA導入で最初に迷う「どれを選ぶか」問題
業務の自動化を進めるうえで、「RPAツールをどれにすべきか?」という悩みは避けて通れません。特に、WinActorとPower Automateは、機能や価格帯の違いが明確でありながら、導入企業の立場によって“どちらがベストか”は変わってきます。
「なるべくコストを抑えたい」
「社内のITスキルに差がある」
「紙・FAX中心の業務が多い」
「Microsoft 365はすでに導入している」
こうした条件によって、選ぶべきRPAは変わります。この記事では、特に中小企業や自治体、教育機関などの導入現場でよく比較される2大ツール「WinActor」と「Power Automate」の違いを、わかりやすく整理します。
さらに、導入に失敗しないための選定ポイントや成功事例も紹介しますので、RPA選定に迷っている方はぜひ最後までご覧ください。
2. RPAとは?WinActorとPower Automateの位置づけ
RPA(Robotic Process Automation)は、人がPC上で行っている定型業務を、ソフトウェアロボットに代行させる仕組みです。エクセルの入力作業、Webサイトからのデータ収集、システム間のコピペ作業など、毎日行う“繰り返し業務”を自動化することで、作業時間とミスを大幅に削減できます。
日本国内では、多くの企業や自治体でRPAの導入が進んでいますが、代表的なツールとして挙げられるのが以下の2つです。
- WinActor(ウィンアクター):
NTTグループが開発した純国産のRPAツール。日本企業の業務文化にフィットしたUIとサポート体制が強みで、自治体・製造・教育・医療など、幅広い業種で導入実績があります。 - Power Automate(旧Microsoft Flow):
Microsoftが提供するクラウド型のRPAツールで、Microsoft 365と連携しやすいのが最大の特徴。OutlookやExcel、Teamsなどとスムーズに連携できるため、すでにMicrosoft製品を導入している企業との相性が良好です。
どちらも強力なRPAツールですが、企業の規模やITリテラシー、業務内容によって向き不向きがあります。
3. WinActorとPower Automateの主な違いを比較
ここでは、導入前に必ずチェックしておきたい5つの観点から両者を比較します。
| 比較項目 | WinActor | Power Automate |
| 対応業務の幅 | デスクトップ操作全般(FAX、紙系含む) | Web/クラウド中心、GUI操作には弱い |
| UI・操作性 | フローチャート式、直感的で初心者向き | 英語ベース、開発寄りの画面構成 |
| 導入・運用コスト | 初期費用あり・ライセンス制(月額数万円〜) | Microsoft 365利用者なら無料枠あり |
| 保守・サポート | 日本語サポート充実、導入支援ベンダー多数 | ドキュメント中心、サポートは限定的 |
| 拡張性・API連携 | API連携も可能だが主に現場向け | Microsoft系システムとの親和性が高い |
ポイントは、**「どの業務を、どこまで自動化したいのか」**という目的に応じて、適したツールが異なるということです。
たとえば、「紙の申請書をスキャンし、社内システムに手入力している」「FAX受信後に複数システムへ登録している」といった業務が多い場合は、WinActorのようなデスクトップ操作に強いツールが向いています。
一方、TeamsやSharePoint、Power BIなどMicrosoft製品とスムーズに連携し、データフローを自動化したい場合はPower Automateが有利です。
4. こんな企業にはWinActor/Power Automateが向いている
WinActorが向いている企業
- 紙やFAXなどのアナログ業務が根強く残っている
- デスクトップ操作を自動化したい(ブラウザやExcel、社内ツールなど)
- RPAを触る社員のITリテラシーにバラつきがある
- 国産ツールの安心感、サポート体制を重視したい
Power Automateが向いている企業
- Microsoft 365(旧Office365)をすでに導入済み
- クラウド連携やSaaSアプリ中心の業務が多い
- ITリテラシーが高く、英語ベースのUIにも対応できる
- APIやWebhookなどの高度な連携を活用したい
選定に迷った際は、自社の“今の業務環境”と“今後の業務デジタル化の方向性”を見比べると、答えが見えてきます。
5. 導入前に確認すべき5つのチェックポイント
RPAツールを選ぶ際には、以下の5つの観点から社内状況を棚卸しすることをおすすめします。
- 自動化したい業務の種類
- 手作業中心(例:Excel操作、ブラウザ入力、PDF処理)か?
- クラウドアプリ間の連携(例:Teams⇔Forms)か?
- 社内ITスキルの状況
- 担当者のITリテラシーは高いか?
- RPA開発に抵抗がある部署はないか?
- Microsoft製品の導入状況
- Microsoft 365を使っているか?
- SharePointやPower BIなどと連携する業務はあるか?
- 運用体制と保守
- IT部門主導で全社展開するのか?
- 各部門で小規模運用するのか?
- 予算と導入スピード
- 月額予算はどの程度か?
- 社内説得や承認フローにどれだけ時間がかかるか?
これらを整理したうえで比較すると、自社にとって最も適したRPAツールが見えてきます。
6. 成功事例:WinActorを選んだ中小企業のケース(仮想)
たとえば、都内に本社を構える従業員80名の製造業A社では、以下の課題を抱えていました。
- 納品書をFAXで受け取り、営業部門が目視で内容を確認
- その内容を毎回、社内基幹システムへ手入力
- 1日あたり平均60件、ミスが頻発していた
同社は当初、Power Automateを検討していましたが、「FAX→PDF→データ抽出→基幹システム入力」という一連の作業がすべてローカル環境で完結していたため、デスクトップ操作の自動化に強いWinActorを選択。
結果、導入から3カ月でFAX→入力の自動化に成功。担当者の工数は月40時間削減され、ミスも激減。現場の信頼も獲得し、全社への横展開が進んでいます。
7. まとめ:選び方の軸を持とう
RPAは、ツールの良し悪しよりも、「自社に合っているかどうか」が成功を左右します。
- デスクトップ操作を含む業務の自動化が必要ならWinActor
- クラウドアプリやMicrosoft製品との連携を重視するならPower Automate
このシンプルな軸を持つだけで、失敗する確率は大きく下がります。
また、WinActorは日本語サポートが手厚く、RPAに不慣れな企業にとって非常に扱いやすいツールです。「まずは一部業務から試したい」という企業には、特に相性が良い選択肢といえるでしょう。
RPAは導入して終わりではなく、“使いこなして効果を出す”ことが重要です。自社に合ったツールを選び、業務効率化の第一歩を踏み出しましょう。